片頭痛とは
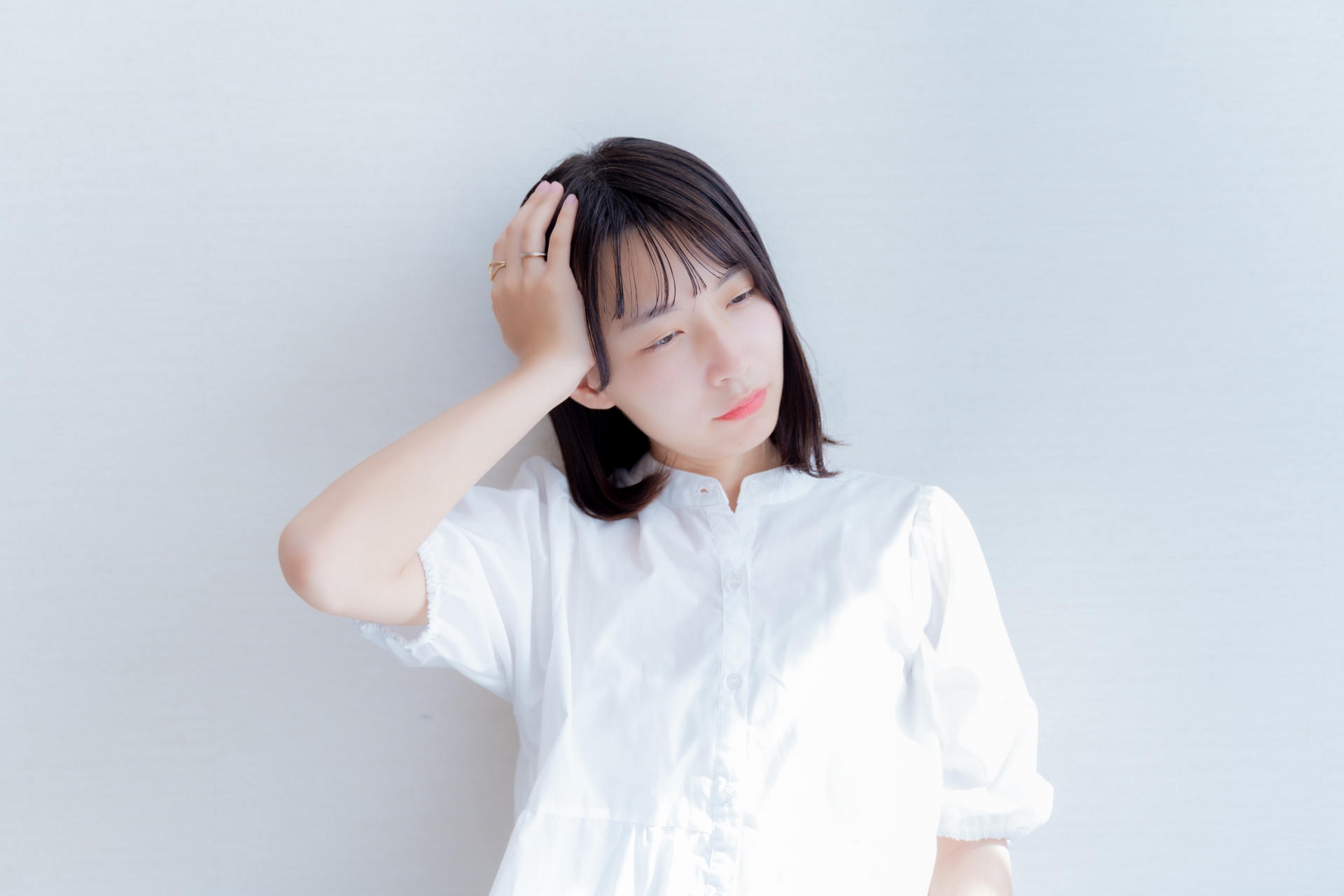 片頭痛とは、何らかの原因で脳の血管が急激に拡張することで引き起こされる頭痛で、「ズキンズキン」と脈打つような痛みが起こる疾患です。最近の研究やCGRPの治療から、CGRPが大きく関与していることは明らかです。痛みは頭の片側や両側に起き、身動きが取れないほどの激しい痛みであるため、日常生活への支障が大きい頭痛です。吐き気や嘔吐、眠気を伴うことや、光や音、臭いなどの感覚が敏感になることもあります。片頭痛は、突然始まり30分から1時間程度で痛みがピークに達し、片頭痛が起こる際には、視界にキラキラとした何かが見えたり、頸の辺りがゾワゾワするなどの前兆を感じることという特徴があります。症状は通常4~72時間程度で治まり、症状が消えると普段と何も変わらず生活が送れます。片頭痛を起こす頻度は人によってさまざまで、数ヵ月に1回程度から、週に数回とかなり幅があります。片頭痛は適切な薬を使うことで、簡単に症状をコントロールできるため、片頭痛かなと思った場合は、受診することをお勧めします。
片頭痛とは、何らかの原因で脳の血管が急激に拡張することで引き起こされる頭痛で、「ズキンズキン」と脈打つような痛みが起こる疾患です。最近の研究やCGRPの治療から、CGRPが大きく関与していることは明らかです。痛みは頭の片側や両側に起き、身動きが取れないほどの激しい痛みであるため、日常生活への支障が大きい頭痛です。吐き気や嘔吐、眠気を伴うことや、光や音、臭いなどの感覚が敏感になることもあります。片頭痛は、突然始まり30分から1時間程度で痛みがピークに達し、片頭痛が起こる際には、視界にキラキラとした何かが見えたり、頸の辺りがゾワゾワするなどの前兆を感じることという特徴があります。症状は通常4~72時間程度で治まり、症状が消えると普段と何も変わらず生活が送れます。片頭痛を起こす頻度は人によってさまざまで、数ヵ月に1回程度から、週に数回とかなり幅があります。片頭痛は適切な薬を使うことで、簡単に症状をコントロールできるため、片頭痛かなと思った場合は、受診することをお勧めします。
片頭痛の原因
片頭痛を起こす原因は明確でないことも多いですが、悪天候や精神的なストレス、強い精神的ストレスからの解放、寝すぎ、寝不足、ホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。女性の場合は、月経周期の決まった時期に片頭痛を起こすこともあります。片頭痛は血管の収縮と拡張によって起こる頭痛であるため、片頭痛の治療薬は血管に関わる薬が多いです。治療薬の中には、抗CGRP関連抗体薬のように、神経伝達物質に働きかけて痛みをコントロールするものもあります。しかし、月経関連片頭痛は難治性になることが多く、改めてお困りの方はご相談ください。
片頭痛の前兆
片頭痛は前兆がある場合があり、片頭痛をお持ちの方の、20~30%は片頭痛が起こる前兆を感じるとされています。前兆はさまざまで、光や視野の一部が欠ける(閃輝暗点)といった視覚的なものや、感覚が鈍くなる、言葉を話しにくくなるといった身体的なものもあります。前兆は5分から1時間程度で消え、その後、頭痛が始まります。このような前兆はない場合もあります。
慢性片頭痛
慢性片頭痛とは、片頭痛の他に、緊張型頭痛などの他の頭痛を合併している状態です。頭痛が毎日のように起こるため、生活の質が大きく下がります。慢性片頭痛の診断基準は、片頭痛と緊張型頭痛などの他の頭痛が月に15回以上生じており、そのうち8回以上が片頭痛の特徴を備えた頭痛であることです。慢性片頭痛の大半の発症原因は、鎮痛剤を長期間にわたって服用することで、脳の痛みの調整機能が低下することで起こる薬物乱用頭痛が関わっているとされています。
片頭痛の診断
片頭痛の診断は、問診によって行います。またMRI検査、血液検査などを行うことがあります。MRI検査は、くも膜下出血や脳腫瘍、もやもや病でないことを調べるために、血液検査は、肝機能や腎機能を測定して、薬を安全に服用できることを確認するために行われます。1回の受診でも確定することもありますが、多くは予防薬やトリプタン製剤の反応性や頭痛ダイアリーパターンから経時的に診断されます。
低用量ピルについて
前兆のある片頭痛がある場合は、低用量ピルの使用は脳梗塞のリスクを高めるとともに、ピル自体が片頭痛の原因となるため、禁忌とされています。婦人科疾患治療の目的で低用量ピルを服用している場合は、継続可否を慎重に検討する必要があるため、通院先の婦人科に相談し、代替手段がない場合は、そのリスクを説明してもらう必要があります。避妊目的で低用量ピルを服用している場合は服用の中止を勧めることがあります。
片頭痛の治療
片頭痛の治療は、痛みの前兆が現れる予感時の内服と痛みが現れる発作時の内服、発作を予防するための内服の3種類があります。
薬物療法
予感時の治療薬
片頭痛の治療薬のトリプタン製剤やラスミジタン(レイボー)を、痛みが起こる前兆の段階で服用すると、血管の急激な拡張が抑えられ、その後の頭痛を抑える効果があります。内服するタイミングをとらえるのにコツがいるため、上手に内服できるようになるため少し時間がかかります。トリプタン製剤の中にもさまざまな種類の薬があるため、医師と相談しながらご自身に合ったものを見つけましょう。発作がいつ起こってもよいように、寝室や職場、鞄や財布の中などに持っておきましょう。2022年にトリプタンの次世代型のジタン(一般名:ラスミジタン、商品名:レイボー)が発売されました。
痛み止め
片頭痛に緊張型頭痛が合併している場合や、トリプタンの服用に失敗した場合はNSAIDsなどの痛み止めを用いることがありますが、効果は限定的です。市販薬やSG顆粒は薬物乱用頭痛へ移行するリスクが高いため使用する際は、服用錠数に注意が必要です。
予防薬
予防薬を毎日服用することで、片頭痛発作が起こること自体を防ぎます。片頭痛の中心となる治療です。片頭痛の発作が月3回以上と頻度が高かったり、何らかの理由でトリプタンが使えない場合は予防薬を使用します。トリプタンの使用頻度が月10回を超えるような状況では、薬物乱用頭痛となるため、薬物乱用頭痛を避けるためにも予防治療を行います。片頭痛の予防薬は、もともと別の疾患の治療に用いられていた薬剤が転用されているものが多いため、副作用に関するデータが多く、比較的安全に使用できるものが多いです。以下に、古典的な従来内服予防薬から提示します。
脳血管拡張薬:ミグシス
カルシウム拮抗薬に分類される血管拡張薬です。効果が現れるまで、1週間程度かかります。
抗てんかん薬:デパケン、(適応外使用:トビナ、リボトリール)
痛み発作に関する脳の興奮を抑制することで作用するとされています。てんかん治療の半分程度の量を用います。定期的な血液検査が必須です。
降圧薬:インデラル
βブロッカーと呼ばれる高血圧・心不全・不整脈の薬です。妊娠・出産・授乳期にも安全性が確保されている薬です。
抗うつ薬:トリプタノール、サインバルタ
トリプタノール(アミトリプチリン)は、長く頭痛治療に使われている抗うつ薬です。サインバルタは、近年発売されたSNRIという抗うつ薬です。両者ともに頭痛予防薬として、使用されます。便秘や眠気などの副作用があります。眠気の副作用は、睡眠が安定するので頭痛改善にはプラスになると考えられます。
新薬:エムガルディ、アジョビ、アイモビーグ
2021年に、CGRP関連予防注射薬が相次いで認可、発売されました。特にエムガルティの2本打ちは、翌日から改善する即効性が印象的です。アジョビは、患者さんからは長期効果で評判が良い印象があります。アイモビーグは、上記2剤で腕が腫れてしまうケースには、完全ヒト化抗体のため、選択される薬です。
漢方薬
漢方薬は片頭痛に有効であると頭痛ガイドラインにも明記されています。片頭痛の治療には呉茱萸湯(ごしゅゆとう)、桂枝人参湯(けいしにんじんとう)、釣藤散(ちょうとうさん)、五苓散(ごれいさん)、葛根湯(かっこんとう)などが適していると考えられています。西洋医学の薬と併用することで補完しあったりより効果的な治療ができます。副作用チェックのために定期的に血液検査を行うことをお勧めします。
その他
片頭痛に伴い、吐き気や嘔吐などのつらい症状がある場合には、その都度対応します。発作時は、制吐剤を併用することが多く、制吐剤自体も頭痛の急性期治療となります。
頭痛の記録
片頭痛の治療を決めるうえで、頭痛の頻度・重症度が重要になるので、可能であれば初診の前に頭痛の大まかな記録をつけておくと、診断が早くできます。頭痛ダイアリーを用いて俯瞰的に管理すると、ご自身で片頭痛と緊張型頭痛の区別ができるようになり、片頭痛の発作回数を正確に数え、トリプタンの使い過ぎを避けることにもつながります。また、女性の場合は、頭痛の記録をつけることで、片頭痛と月経との関係性がわかります。近年ではスマートフォンで頭痛管理ができるアプリもあります。
生活の工夫
 規則正しい生活や運動習慣、適切な睡眠管理、ストレスを溜めないことは重要です。たとえば食事の改善に取り組む場合、血管の収縮や拡張に影響がある食べ物を避けると良いでしょう。
規則正しい生活や運動習慣、適切な睡眠管理、ストレスを溜めないことは重要です。たとえば食事の改善に取り組む場合、血管の収縮や拡張に影響がある食べ物を避けると良いでしょう。
摂った方が良いもの
マグネシウム
煎りごまやひじき、玄米、大豆、海藻類などはマグネシウムを多く含みます。
ビタミンB2
うなぎやレバー類、カレイ、ほうれん草、納豆などはビタミンB2を多く含みます。
避けた方が良いもの
チラミン
赤ワインや熟成チーズ、チョコレート・ココアなどのカカオ製品、漬物類、発酵食品、燻製魚、トリのレバー、イチジク、ナッツ類、柑橘類はチラミンという成分を含むため避けましょう。ナツシロギクの摂取が有効というデータもありますが、妊娠中はリスクがあります。
早めの受診をお勧めします
片頭痛は、根本的な原因を解消する治療薬があり、治療を受けることで症状を緩和できます。また、強い頭痛は他の深刻な疾患によってもたらされることもあるため、強い頭痛がある場合は、早めに専門医を受診して適切な治療を受けることをお勧めします。











